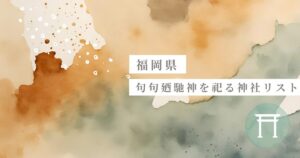(訪問日:2023年4月)
本州生まれで、大人になってから福岡県にやってきた自分にとって、九州は未知の世界だった。
国東半島はさらに謎。
観光情報から見聞きする六郷満山や磨崖仏など、ミステリアスな史跡ばかり。
それが福岡県の大分県寄り「豊前市」に移住してから国東半島への距離が縮まった。
移住前に一度だけ立ち寄った国東市の成仏寺へは、その時には「次」があるとは思っていなかった。
それが2021年に豊前市に移住した2年後に、再び訪れることができた。

駐車場から道路を挟んでお寺側をむくと、二対の仁王像が目に入ってくる。
前来た時と同じだ。
あの時は子どもたちが仁王像の胸部を見て「むねぼねだー」と言っていた。
よく覚えている。
Webサイト「日本遺産 鬼が仏になった里『くにさき』」によれば、成仏寺の正式名称(?)は龍下山成仏寺らしい。
龍が棲んでいたという岩屋にできたことからそう名付けられたそうだ。
本堂や岩屋は修正鬼会の舞台ともある。
修正鬼会はかつて六郷満山で催されていたという春を迎える伝統行事だが、今は成仏寺を含め限られた寺院でしか催されていないそうだ。
修正鬼会とは
修正鬼会は、国東半島の六郷満山寺院を中心に行われてきた春を迎える伝統行事です。地域では「鬼会(おにお)」とか「鬼夜(おによ)」と呼んだりもします。
平安時代に都の各仏教寺院で「修正会」という正月の法会が行われるようになり、各地の寺院にも広がり、鎌倉時代にはこの国東半島地域に入っていたようです。そして六郷満山寺院では、この地域で行われた「鬼会」という行法と結びつき、独自の「修正鬼会」が生まれたと考えられています。
現在、寺々に残されている鬼会面等から、江戸時代の初め頃から盛んに行われていたようです。
六郷山の寺院は、決して大きな寺ではありませんでしたが、領主の厚い保護を受け、領地や多くの僧を抱えていたことから、各寺院で「修正鬼会」を行うことができました。しかし、明治時代になると、保護する領主もなくなり、寺僧も減少したことから、六郷山の寺々は東・中・西組に分かれ、各組内で相互に加勢しあう方法をとり、およそ20の寺院で「修正鬼会」を行っていました。現在では東組が国東市の成仏寺と岩戸寺で交互に行い、西組が豊後高田市の天念寺で行うだけとなっています。
修正鬼会は寺の僧侶だけでなく、地域の人々が様々な役割を担っています。このことは、六郷満山寺院と地域の結びつきの強さを示すものと考えられています。
仏教儀式でありながら農耕儀礼や庶民信仰をも含んだ儀式として、昭和52年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。
Webサイト「六郷満山開山1300年〜神仏習合の発祥の地 国東半島宇佐地域〜」 から引用

この時訪れたのは4月上旬のようだが、ツツジがよく咲いていた。


同じものが一つとしていないという、数多くの仁王像が国東半島内に存在する。
そのなかでも、この成仏寺だけ、二対の仁王像が寺の門を守っているそうだ。

本堂に向かって左側、奥の院に続く階段手前には歴史を感じる庚申塔、石仏が立っていた。

一番左は庚申塔…と思う。
国東半島の庚申塔巡りをしている人のブログでそう書かれていた記憶がある。
ソースが分かったら追記しよう。

ここから先は奥の院へ続く階段がある。

上っていくと、突き当りが見えてくる。

後ろを振り返ると、駐車場が見えた。
なかなかの高さだ。


何も書かれていないけど、こちらが奥の院だろうか。
崖のすぐ下にあった。

五輪塔や石祠がたくさん並んでいた。

階段を降りて、スタート地点であるお寺の正面に戻った。

そこからは、国東半島のほぼ真ん中にある両子山が見えた。
後から知ったことだが、成仏寺の向かい側には「成仏岩陰遺跡」があるそうだ。
縄文時代の人骨が発掘され、かつては禁忌の地として地元の人に恐れられたという。
その場所に2014年、地元の人達からの後押しでそこに芸術作品が設置されたらしい。
やはり気になる国東半島だ。
成仏寺のアクセス
〒873-0535 大分県国東市 国東町成仏1140−4