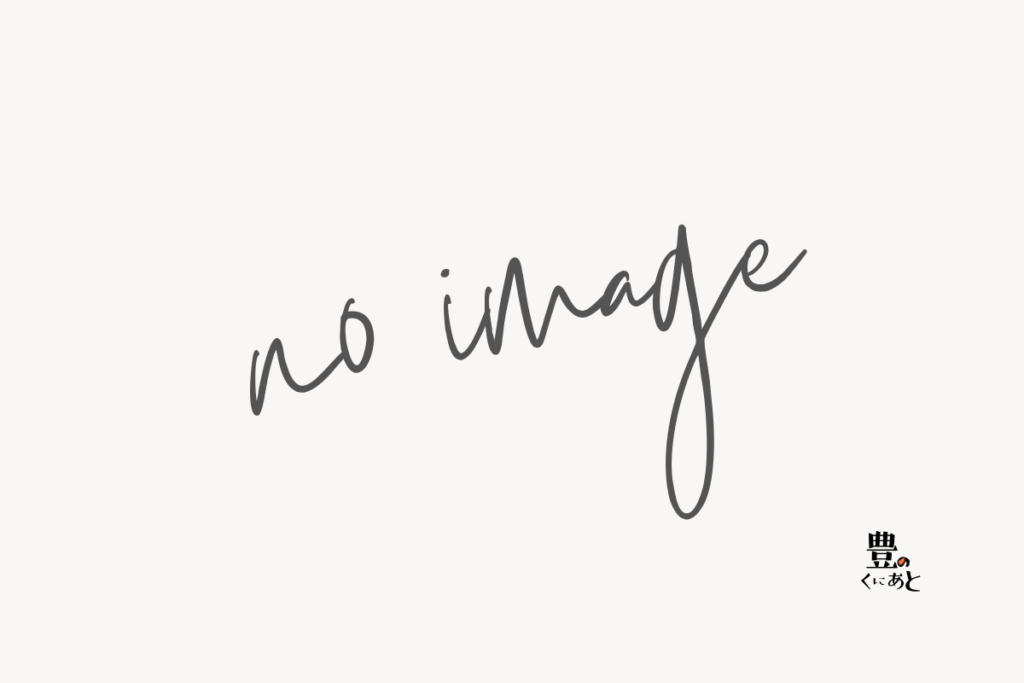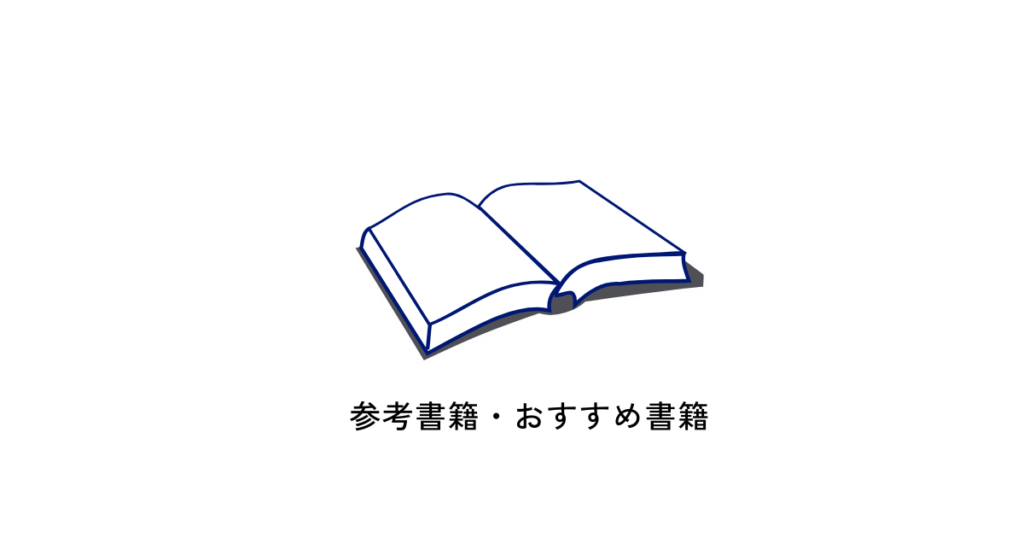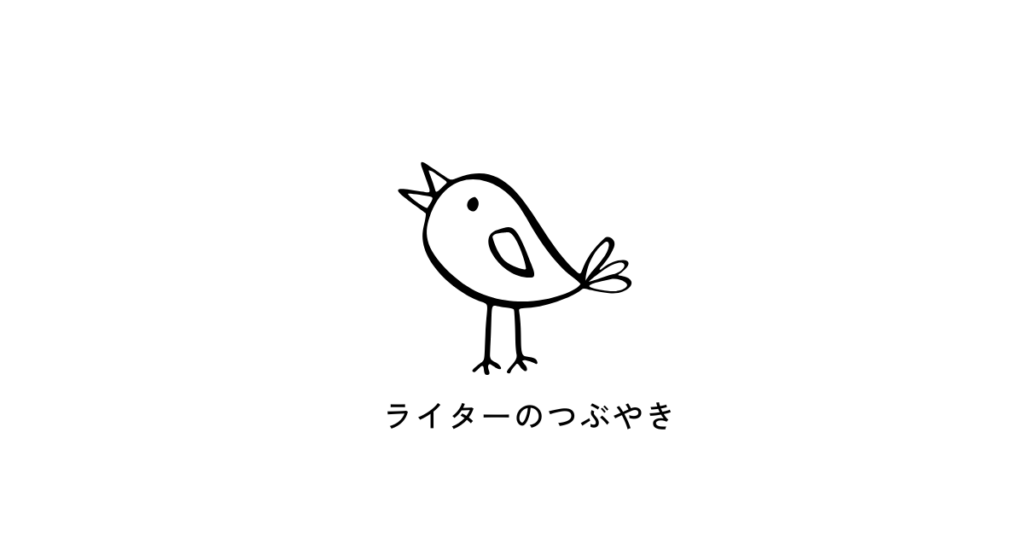古代史の謎– category –
-

旧・豊前エリアの貴船神社と高倉下(たかくらじ):龍神信仰と古代航路が繋ぐ「高倉」の謎
旧豊前国に数多い貴船神社 豊前市に移住してから、大分県中津市と宇佐市、そして周辺にやたら多い「貴船神社」を不思議に思っていました。 大分県中津市、宇佐市、そして周辺の旧豊前国エリアには、関西出身の私が驚くほど多くの貴船神社が存在します。 京... -

神社にある二本の石柱の名前は「標柱(しめばしら)」
20年ほど住んだ北九州市から豊前市に移住して、立ち寄った神社を見ると神社の鳥居の前や社殿の前に二本の石柱が立っていることが気になりました。 北九州では意識していたから目に入らなかったのかもしれませんが、豊前エリアにやってきて、やたらと目につ... -

巴が三つ並んだ三つ巴紋_「3」の数字にはどんな意味が?
国東半島の北端で見つけた「右三つ巴紋」の謎を追って、これまで考察記事をいくつも書いてきました。 宇佐神宮や多くの八幡系の神社が左三つ巴紋であるのに対し、なぜか違う向きの巴紋があることに気づき、北部九州エリアを中心に神社仏閣を巡ってきました... -

筑紫君磐井と「石・丹」:ヤマトに抑え込まれた九州王権の痕跡を追う
古代史に突如姿を現し、ヤマト王権と対立した勢力・筑紫君磐井。彼の名に刻まれた「石(磐)」という語、そして背後に見え隠れする「夷(い)」の概念。これらを手がかりに、旧豊の国エリアに残された痕跡から、彼の正体に迫ることはできるのでしょうか。 ... -

神社のルーツとは?いつ生まれた?素朴な疑問に答えてくれる本「神社に秘められた日本史の謎」
初詣にお宮参り、七五三、厄除けと、これだけ私たちの暮らしに身近な「神社」ですが、なぜ神社ができたのか、いつできたのかなど、ちゃんと学ぶ機会が今まで一度もありませんでした。 よく分からないというより、あるのが当たり前で、意識もしていなかった... -

八面大王は「やめのおおきみ」とも読める?では大分県中津市の八面山とは
漢字というものは、自分が意識せずとも頭の中に意識が固定化されるものだと思った。 先日ニュースで聞いた「福岡県志賀島」、普段は「鹿」と関係ないと思っていたのに、音だけ聞くと「あれ、『しか』って『鹿』?」と普段と違う意味合いを感じた。 音が同... -

磐井の乱後の安曇族と磐井葛子の行方を調べるならこの本「信濃安曇族の謎を追うーどこから来て、どこへ消えたかー」
以前から気になっていた、古代最大の内乱といわれる「磐井の乱」。 歴史の教科書では、日本を裏切って外国側についた悪者のように書かれていた筑紫君磐井ですが、近年になり、歴史好きの方からも「磐井は九州の英雄だった」という情報を聞きました。 ほか... -

数少ない牛頭天王の本「牛頭天王信仰の中世」
先月、移住元の北九州市に行った時、大型書籍販売店で見つけた「鈴木耕太郎著 牛頭天王信仰の中世」を購入しました。 「神でも仏でもなく、中世に突如顕われた牛頭天王の謎に満ちた信仰世界を中世神話の視座から読み解き、その深層へと迫る注目の書。」 ... -

英彦山(ひこさん)の(ひこ)から連想した「彦島」、「彦星」つながり
北九州市に住んでいたときに「英彦山(ひこさん)」の存在を知った。 当時、家族が勤めていた会社のトップが毎年詣でる場所と聞いたからだ。 何か特別な場所なのだろうか、しかし「英彦山」って「ひでひこさん」って読んでしまうなと思っていた。 その後、... -

大分県中津市の丹生神社貴船宮と、日本最古の龍神を祀る奈良県吉野郡 丹生川上神社上社が同じ右三つ巴紋
先日、神楽を見に行った神社の名前が「丹生神社」だったので驚いた。 私はずっと右三つ巴紋に意味があるのかと思い、情報を追っていのだけれど、奈良県吉野郡「丹生川上神社上社」の社紋は「右三つ巴紋」、そして先日の中津市の丹生神社貴船宮にも、古い右...