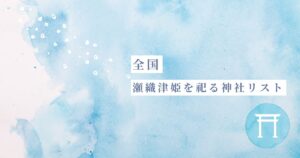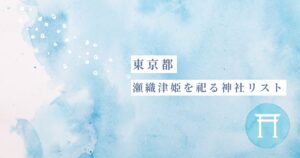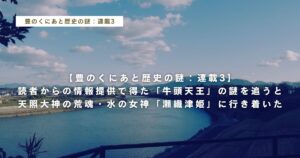疫病除けの神として知られる牛頭天王(ごずてんのう)の総本宮、廣峯神社(ひろみねじんじゃ)が、なぜ兵庫県姫路市というこの地に鎮座するのか、という疑問は、その信仰の広がりを考える上で重要な論点です。
この素朴な疑問に対し、これまでに集めてきたキーワードから、中臣氏(後の藤原氏)と龍神信仰がこの地で交差していた可能性を考察します。
目次
牛頭天王は、日本の神である素戔嗚尊(スサノオノミコト)と習合し、疫病退散の守護神として全国で篤く信仰されてきました。その総本宮が廣峯神社である理由を探る一つの手がかりが、周辺の地名にあります。
「中臣」の痕跡: 廣峯神社からほど近いたつの市揖保町には、中臣(なかじん)という地名と、中臣城の跡が残っています。
古い読みの維持: さらに、同じく揖保町中臣にある中臣印達神社(なかとみ いたてじんじゃ)には、「なかとみ」という古い読みが残っています。
この「中臣」という地名は、日本の古代史を彩る有力氏族、中臣氏(後の藤原氏)との繋がりを示唆している可能性が考えられます。

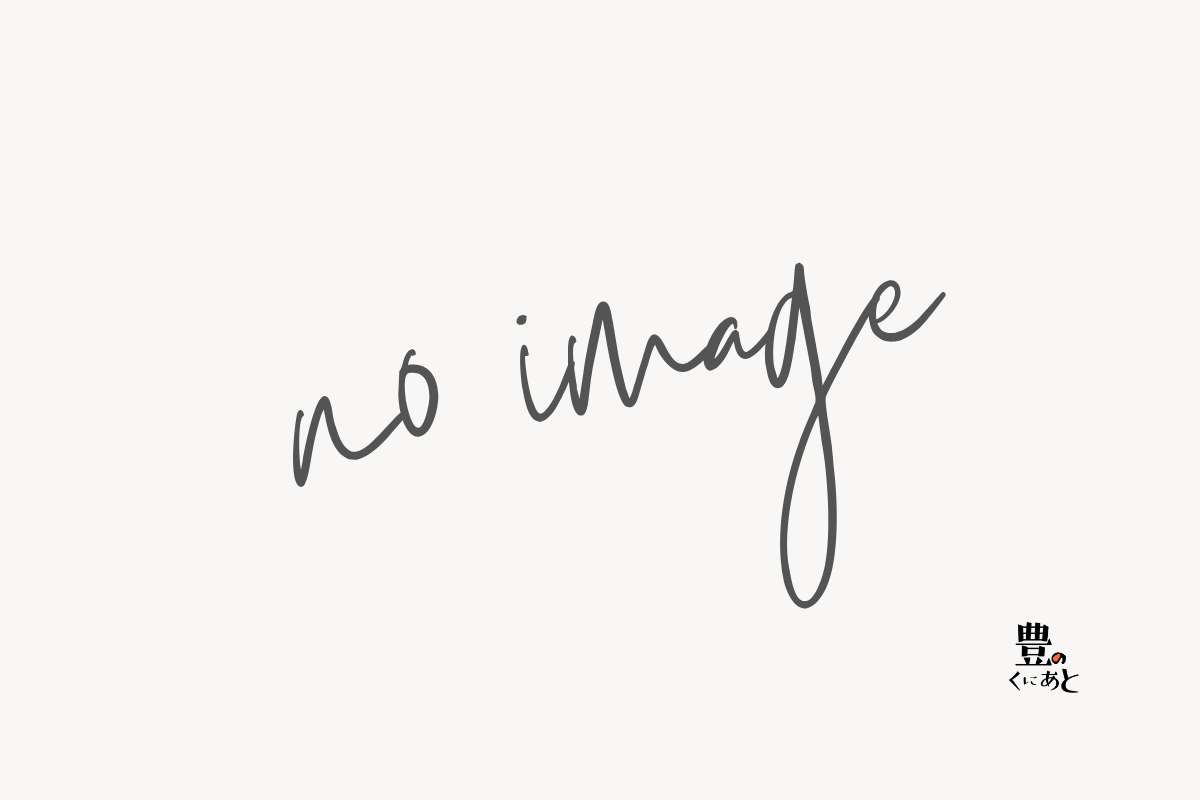






![ChatGPTにポストカード用のディスプレイ台のデザインをお願いして手作り[ morriss の素材屋さん アソート小袋使用 ]](https://toyonokuniato.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2241-300x225.jpg)