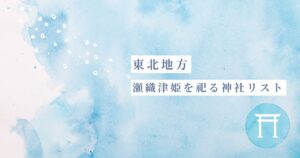先日、神楽を見に行った神社の名前が「丹生神社」だったので驚いた。
私はずっと右三つ巴紋に意味があるのかと思い、情報を追っていのだけれど、奈良県吉野郡「丹生川上神社上社」の社紋は「右三つ巴紋」、そして先日の中津市の丹生神社貴船宮にも、古い右三つ巴紋、それに一部だけ残された石灯籠があった。

古代には、朱の原料となる「丹」を追って、「丹」を取り尽くしたらまた別の土地に「丹」を追って移動する一族がいたそうだ。
「丹」を精製できる技術を持ち、移動ができる一族がいたのは間違いないようだ。
丹生神社、龍神(高龗神・闇龗神)、そして右三つ巴紋。
以前からこのエリアに残る木の国(紀の国)の痕跡のように思えていた、「熊野」ともつながっているのだろうか。
目次
この記事を読んでいる方におすすめの記事
宇佐神宮と逆向きの右三つ巴紋の関連記事と連載記事まとめ↓
あわせて読みたい

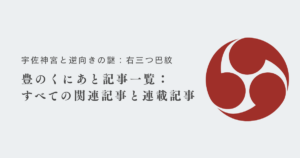
【宇佐神宮と逆向き・右三つ巴紋】豊のくにあと記事一覧:すべての関連記事と連載記事まとめ
「豊のくにあと」をご覧いただきありがとうございます。 このページは、偶然見つけた宇佐神宮とは逆向きの右三つ巴紋について調べた記事をまとめて掲載しています。 右...
右三つ巴紋の違いを専門家に尋ねてみても分からなかった↓
あわせて読みたい


歴史の専門家にも右三つ巴紋の謎を尋ねて返ってきた言葉は「さぁ、考えたこともない」。だから自分で調...
「なぜ宇佐神宮とは逆向きの巴紋(右三つ巴紋)があるんでしょうか?」 私がこれまで巡ってきた北部九州の神社のなかに、宇佐神宮とは逆向きの巴紋があることに気づき、...
歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓
あわせて読みたい


豊のくにあと 歴史の謎ガイド
こんにちは、「豊のくにあと」運営者の「ぶぜんノート」です。 このページをご覧いただいた方は、おそらくこのサイトを何かのキーワードで探しているところ、たどり着い...