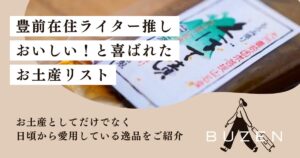春日灯籠(かすがとうろう)は、日本の石灯籠の中でも特に有名で、美しい造形と歴史の深さを持つ様式です。
その名の通り、奈良の春日大社(かすがたいしゃ)が発祥の地とされています。
1. 春日灯籠の歴史と起源
春日灯籠の起源は、平安時代まで遡ります。
春日大社では、奈良時代から多くの灯籠が奉納されてきましたが、室町時代以降に現在の春日灯籠の原型が確立されたと考えられています。
春日大社は、藤原氏の氏神を祀る神社であり、古くから貴族や武士からの信仰を集めてきました。
彼らが神前へ奉納する灯籠は、徐々に定型化され、その独特の様式が「春日灯籠」として広まっていったのです。
特に室町時代から江戸時代にかけて、その人気は高まり、各地の神社仏閣、庭園、さらには個人の邸宅にも設置されるようになりました。
2.春日灯籠の基本的な構造と特徴

春日灯籠は、主に以下の6つの部分から構成されています。この各部の名称と役割を理解すると、その美しさがより深く感じられます。
宝珠(ほうじゅ)
一番上の玉ねぎ状の部分で、仏教の宝珠を模しています。
笠(かさ)
宝珠の下にある、屋根のような部分です。
六角形になっているのが大きな特徴で、反りが美しく、雨水から火袋を守る役割があります。
この六角形が、他の灯籠との識別点にもなります。
火袋(ひぶくろ)
灯りを灯す部分で、通常は石の板を組み合わせて作られています。
灯り取りのために透かし彫り(月、三日月、鹿、雲などのモチーフが多い)が施されており、夜にはそこから幻想的な光が漏れ出します。
中台(ちゅうだい)
火袋を支える台座です。
竿(さお)
中台を支え、地面から灯籠全体を高く持ち上げる柱状の部分です。
円柱形が一般的で、すっきりとした印象を与えます。
この竿の長さによって灯籠全体の印象が大きく変わります。
基礎(きそ)
灯籠全体を支える一番下の土台です。
安定感を与える重要な部分です。
春日灯籠の大きな特徴は、「六角形の笠」と「円柱形の竿」にあります。
また、全体的に細身でスマートな印象を与えることも多く、繊細な美しさが際立ちます。
3. 春日大社と灯籠
春日大社には、2000基もの石灯籠と1000基もの吊り灯籠があり、日本で最も多くの灯籠が奉納されている神社です。
これらの灯籠は、信者によって奉納されたもので、年に2回、節分万燈籠(せつぶんまんとうろう)と中元万燈籠(ちゅうげんまんとうろう)の際に全ての灯籠に明かりが灯されます。
その光景は息をのむほど幻想的で、多くの人々を魅了します。
春日大社の灯籠は、寄進者の名前や寄進された年代が刻まれており、歴史の証人としても非常に価値があります。
4. 庭園における春日灯籠
春日灯籠は、その優雅な姿から、日本庭園においても非常に人気の高い灯籠様式です。
特に、池の畔や石組みの間、あるいは茶室の露地(ろじ)などに設置されることで、庭園に奥行きと趣を与えます。
自然石や苔との調和も美しく、夜には優しい光で庭園を照らし、幻想的な雰囲気を演出します。
5.春日灯篭=祓戸形?
「六角石灯籠のうち、奈良・春日大社のものが『祓戸形』と呼ばれるものがある」という情報を見つけました。
このWebサイトで調べているキーワードに含まれるので、気になる情報です。