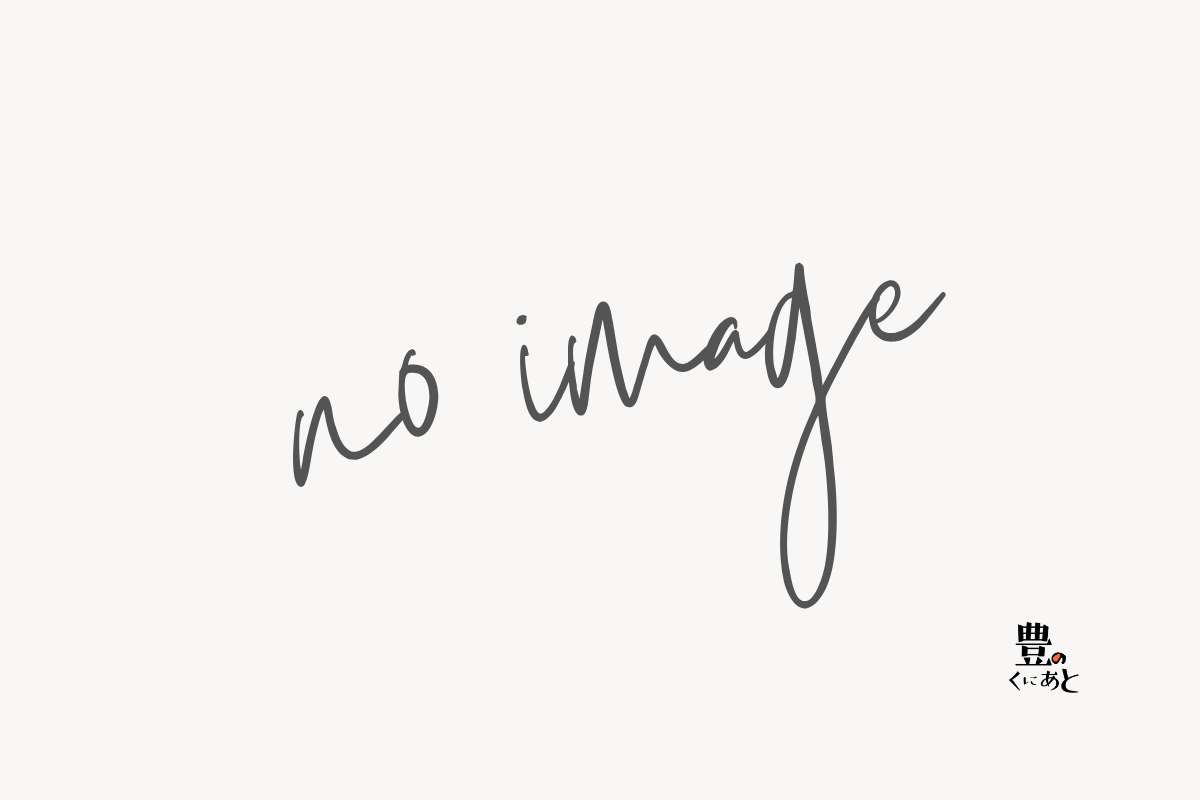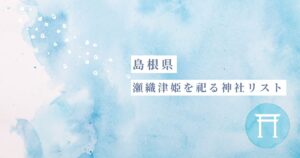日本の歴史を動かした一大勢力、藤原氏。その源流である中臣氏(なかとみうじ)が、現在の福岡県東部を含む古代の豊前国に、重要な接点を持っていた可能性を探ります。
この考察は、後に藤原氏の系譜を汲む宇都宮氏がこの地を治めた歴史とも響き合います。特に、古代の地名「仲津郡(なかつぐん)」と「中臣村」の存在が、この地域の古代史に隠された謎を解く手がかりとなるように見えます。
仲津郡に残る「中臣村」の記述
現在の福岡県行橋市東部から京都郡豊津町・犀川町あたりに相当する古代の豊前国には、仲津郡(なかつぐん)が存在しました。
この仲津郡には、藤原氏の源流である中臣氏と関連する、非常に興味深い記述が残されています。
『豊後国風土記』には、豊国の祖である菟名手(うなで)が仲津郡の「中臣村」に至った際に祥瑞が現れたと記されています。
中臣氏とは: 中臣氏は飛鳥・奈良時代に祭祀を司った氏族であり、後に藤原氏の源流となります。
現在の中津市(古代の下毛郡)と仲津郡は地理的には異なりますが、この郡内に「中臣村」という地名があったという事実は、中臣氏、あるいは祭祀を専門とする集団が、この豊前国の地に存在していた可能性が考えられます。
仲津郡の豪族と渡来系文化の接点
当時の仲津郡には、秦部(はたべ)氏や膳(かしわで)氏など、地方の有力な豪族がいました(『大宝二年(702)の戸籍』など)。
中央で祭祀の地位を確立した中臣氏が、地方豪族とどのような関係を築いていたかは不明ですが、「中臣村」という地名があることから、この地が神聖な祭祀の場であった可能性が考えられます。
また、仲津郡(現豊津町)にある7世紀末建立の上坂廃寺からは、百済系の瓦が出土しています。これは、この地域が古代から渡来人との交流が盛んであったことを示しており、祭祀を司る中臣氏と、渡来系の技術や文化との間に、何らかの関係性が存在していた可能性も視野に入ってきます。
藤原氏信仰の痕跡「春日灯籠」
藤原氏とこの地の繋がりを示すもう一つの興味深い点は、春日信仰の痕跡です。
藤原氏の氏神である春日大社は、神の使いとされる鹿で有名です。
以前、春日神社ではない福岡県内の神社で、鹿、月、雲などが刻まれた春日灯籠が見つかりました。
なぜ、ここにと思う神社でした。
この春日灯籠の存在は、藤原氏の勢力や信仰が、中央の奈良から遠く離れたこの豊前地域にも及んでいたことを結びつけているように見えます。
「中臣村」という地名、そして後の時代にみられる春日信仰の痕跡は、藤原氏の源流である中臣氏が、豊前地域と単なる偶然ではない、深い歴史的・祭祀的な関わりを持っていた可能性が考えられます。
この地域の古代史を解く上で、重要な手がかりとなりそうです。
この記事を読んでいる方におすすめの記事
中臣氏・藤原氏の関連記事・連載記事まとめ↓
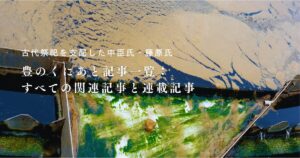
牛頭天王と藤原氏(中臣氏)と龍神信仰の交点が姫路にある?↓

歴史の謎の記事をまとめて読む↓