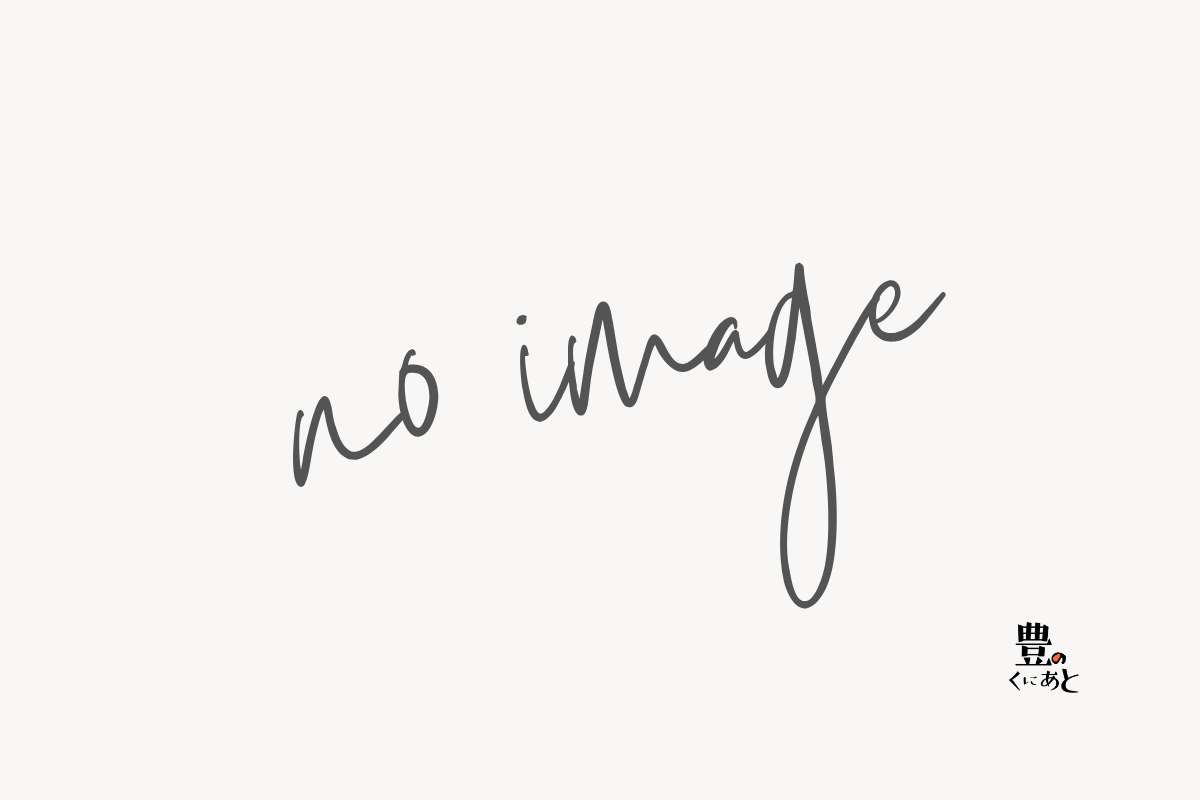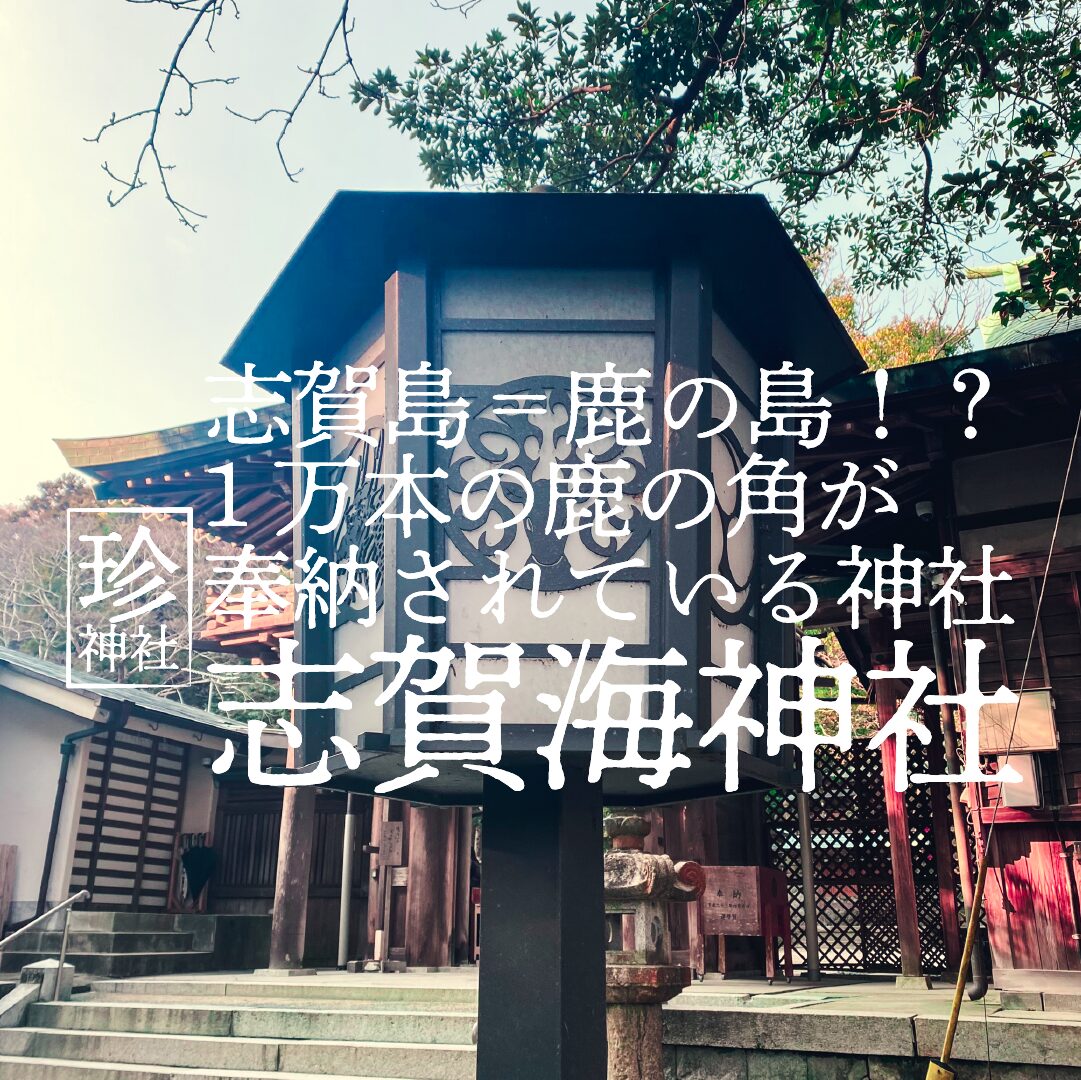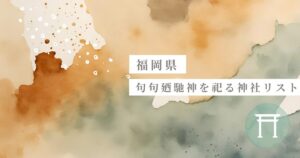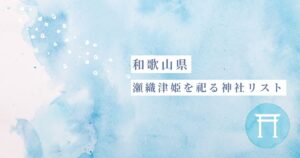北九州市に住んでいたときに「英彦山(ひこさん)」の存在を知った。
当時、家族が勤めていた会社のトップが毎年詣でる場所と聞いたからだ。
何か特別な場所なのだろうか、しかし「英彦山」って「ひでひこさん」って読んでしまうなと思っていた。
その後、史跡巡りから歴史の謎にどっぷりつかっていくわけだが、地名を変えられているんじゃないかと思う場所が結構あった。
「志賀島(しかのしま)」がそうだ。
鹿の角が一万本奉納されていたそうだが、いくらなんでもその数の「鹿」の角があれば、鹿と関連するのは間違いないだろうと素人でも思う。
でも不思議と「志賀島」と思っているうちは、そんなこと意識をしたことがなかった。
字を変えられると、やはり分からなくなる。
だからだろうか、「英彦山」も気になっている。
古くは「日子山」、それから「彦山」、さらに「英彦山」へ変化したらしい。
「彦山」だけなら読みやすいのに、なぜ「英」がつけられたのだろうと。
そうずっと疑問に思っていたら、あるとき「英彦山」のニュースの後、山口県の「彦島」のニュースが流れてきて、「あっ」とした。
「彦」つながりだ。
北九州に住んでいた時でも、彦島は遠く、よく知らなかったけど、調べてみたら海に関する神社が多い。
えびす神社に、こんぴらさま。
「日」につながる海。
「彦」とつながる言葉は他に「彦星」もある。
織姫と彦星、織姫は「瀬織津姫」と同一視する説もあり、以前からちゃんと調べないとと思っている。
北部九州に残る「彦」について、また調べて分かることがあれば記事にしていきたい。