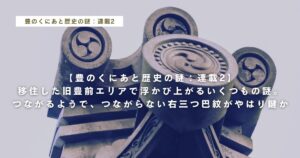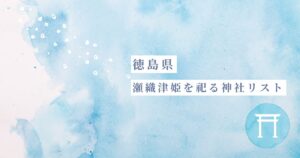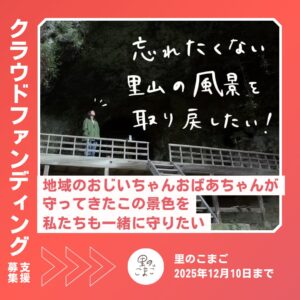
(この記事はnoteで2022年7月23日に公開した記事を一部移行・編集したものです)
大分県中津市のシンボルである八面山は、八幡信仰の始まりの場と言われている。
山の中には今なお多くの史跡が残されているが、謎が多い霊山とされている。
その八面山に平安時代からの歴史ある場所、猪川内岩屋堂へ行くことができた。
その時のことをこの記事でお伝えしたい。
猪川内岩屋堂はクラウドファンディングにより修復が実行された
猪川内岩屋堂は、地域の人さえどこにあるのか分からなかったお堂であったそうだ。
それを八面山エリアで地域おこし協力隊をしていた秦(はた)さんが見つけ、クラウドファンディングを実行し、多くの方々の協力のもと修復したらしい。
八面山には、平安時代からの歴史ある場所、猪川内岩屋堂があります。八面山修験の回峰路の一つになっており、そこから八面山信仰の中心である箭山神社を仰ぎ見ることができる信仰の装置としてもわかりやすい場所にあるお堂です。
地域の人たちにとっては、弘法大師空海のお祭り「お接待(おこぼさま)」の場所として大切に守られていました。
ただ現状は、お堂を構築していた木材が朽ち落ち、木の仏像が野晒しにされているような状態です。昭和60年以降の文献で、朽ちかけたお堂の写真が見られます。もうそのころには集落の減少とともにお堂も忘れ去られていたものだと思われます。
千年以上繋いできた歴史を後の世代につなげない悔しさのようなものもあります。
そこで、地域内外の多くの方々に当事者意識を持ち関わっていただきながら修復を行っていこうと企画を立ち上げました。
平安時代からの歴史ある場所で、八面山修験や地域の人にとって大切な祈りの場所であったのに、時代とともに忘れられ荒れたお堂を修復したと聞いていた。
地図を見てもなかなかよく分からないでいたら、折よく新旧地域おこし協力隊隊員が集まる時に案内していただくことができた。
待ち合わせしてから猪川内岩屋堂へ
地域おこし協力隊の方から、待ち合わせに指定された場所は元限界集落。

道路わきに車を停めて隊員の方を探すと上のほうから声が。
なんと皆さん、お堂を修復中だった。
後で地図を確認したところ、「八面山聖母八幡比咩神拝所」のよう。
ここから隊員の方の車に同乗し、数分離れたため池付近の空き地に車が停められ、そこから徒歩で猪川内岩屋堂へ向かった。

池の土手の向こう側の山の岩肌にお堂がある。

ハードめな道だったけど、地域おこし協力隊の尾上さんと前任者の秦さんは、154年ぶりの修験道の行事「八面山峰入り」の参加者で全3日の行程を歩いたという頑強さ。
足腰の強さが違う。

お堂の中にはクラウドファンディングで支援してくれた方々の名前が並んでいた。

窓からは八面山が見えた。
形が独特の山だ。
どこから見ても同じ形に見える。
「ここからの眺めがよくてね。修復のとき高さを上げたんですよ」とは秦さん。

お堂の中には秦さんが言っていた平安時代の木像や石仏も八面山に向かって安置されていた。
地域おこし協力隊のメンバーによれば、このような平安時代クラスの木像がまだまだ山の中にあるらしい。
観光資源として活用するため、次の時代につなげるために修復活動をしているそうだけど、費用や手間から障害はありそうだった。


同行したタリア人女性(ドイツ・ベルリン自由大学の文化人類学の研究生)は「なんて素晴らしいところに連れてきてくれてありがとうございました!」と大変喜んでいた。
もっと知られてほしい史跡や山、そして人の取り組みだ。
↓豊前市に在住していたイタリア人女性

猪川内岩屋堂のアクセス
〒871-0103 大分県中津市三光田口