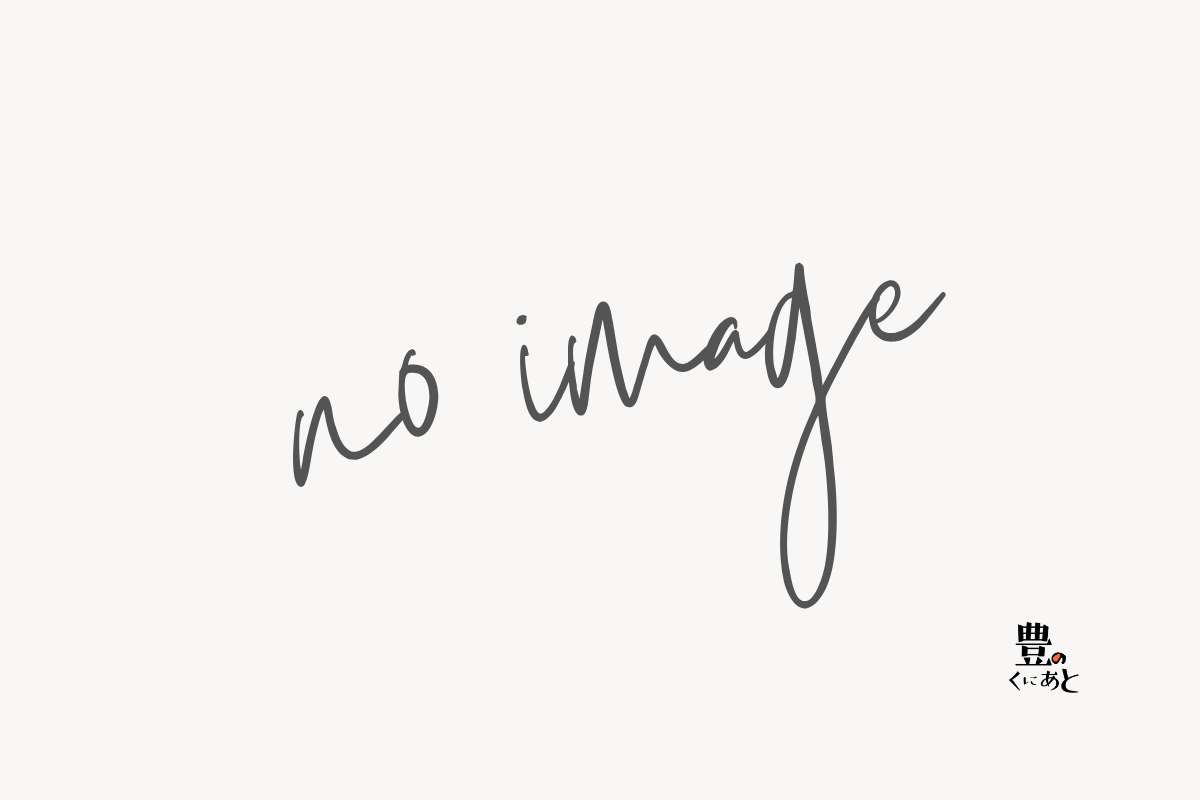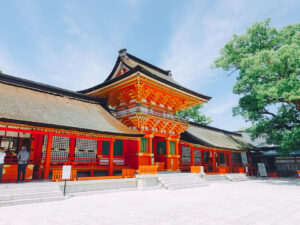「なぜ宇佐神宮とは逆向きの巴紋(右三つ巴紋)があるんでしょうか?」
私がこれまで巡ってきた北部九州の神社のなかに、宇佐神宮とは逆向きの巴紋があることに気づき、自分で調べてもはっきりしたことは分からなかったので、歴史の専門家に尋ねたことはあります。


しかし答えは得られませんでした。
というより、「考えたこともありません」「さぁ、何ででしょうね」「単に間違ったんじゃないですか」と、あまり重要と思われない方が多かったように思います。
説明が拙いせいで、専門家には響かないだけなのかもですが…
しかし右三つ巴紋がある神社が複数存在すること、筑後エリアの正八幡宮も右三つ巴紋であることから、何らかの関わりがあるのではないかと、疑問が消せません。
歴史の専門家が気にならないのだとしても、答えがはっきりしないのでずっと気になって仕方がないのです。


専門家からの返答が「考えたことがない」「さぁ」なので、どうもスッキリしない。
調べてくれたわけではない、知っているわけでもないのだからモヤモヤが残りました。
また、右三つ巴紋に関係しそうな豊前エリアの貴船神社の多さについて尋ねても、「昔は水不足が多かったから、それで多いんじゃないですか。ため池多いし」と言われましたが、大きな河川沿いにもそれこそ沢山の貴船神社があるのです。

そんな細かいことが気になってしまうのは、プログラマー時代に、天才で仕事に厳しい上司から「なぜこのコードだと動かないのか、なぜかを確認しないとだめでしょう」「『無い』と最初から思うな、あらゆる事象を『ある』かもしれないと前提を変えて確かめることが大切」と叱責されて以来、「違うのならその理由とは?」をつきつめるようになったからかもしれません。
古代史は文書が残っていない時代だから、証明に限界があり、既に調べ尽くされている。だからこれ以上調べても仕方がない。宇佐神宮系が絡むと面倒__この現代というのに、そんなふうに仰る方もいました。
大変正直な気持ちとしては「そこを調べるのが研究者ちゃうんかい」でしたが、プログラマーの世界と、歴史研究の世界はおそらく構造が違うのだと思います。
「歴史において微細な違いは異常値無しとされる」「史料が無い時代の研究では証明ができない」、などと、その世界特有の理由があるのでしょう。
以前、ある宮司さんから「歴史の専門家は史書にない時代のことは『無い』のだといいますが、神社は?古墳は?まつりは?字が無い時代から『ある』ではありませんか」と聞き、私もその言葉に納得しました。
だって「ある」のに。
理論上無いといって、目の前にあるものを無いことにするなんて、それこそこれだけ身近にある神社や古墳やまつりの否定ではないかと思ってしまいました。
文書が駄目なら、今の時代様々な技術はありますし、AIだって発達している。
今のあらゆる技術を組み合わせても、本当に調べられないものでしょうか。本当に調べる余地ゼロなのか。
それでも私にかけられた言葉のうち「そもそもあそこに水が湧き出たら水の神様、川が近いところには川の神様、昔の人の認識はそんなものだったと思いますよ」
これは逆に謎を追うヒントになりました。
たしかに昔の人たちは字を書く人などほとんどおらず、日本最古の歴史書といわれる「古事記」「日本書紀」を書いた人なんて本当にごくごく一部の特別な人でした。
その後の時代においても、庶民まで字を読み書きできるようになったのは、長い日本の歴史のうちほんの最近ということになるでしょう。
ということは、たとえば水の神様がどんな神様なのかは、その土地に住んでいた氏族のルーツが影響しているのではないかと思ったのです。
神社では、氏族が崇拝されていた神や、ご先祖様が御祭神とされたり、時に敗者側を祟り神として祀られてきた歴史があるようです。
(以下の書籍が「神社とは?」「なぜこんな形式になった?」という疑問に答える形で説明してくれているので分かりやすいです。)
ただ明治時代に御祭神が多く書き換えられたという情報もありますが、その書き換えに「人」が絡んでいるのなら、その書き換えは荒唐無稽なものではなく何らかの法則はあるのではないか、とも。
古代の人が恐れ「神」と感じた自然に人格を与えた「人」の存在があって、そして字が無い時代だからこそ、形_目に見えるもので残そうとしたのではないでしょうか。
それが右三つ巴紋であったり、二本の石柱であったり、狛犬であったり、石灯籠であったりしないだろうかと、色々な歴史のかけらをこのサイトに集めています。
以前、豊前市に滞在していたベルリン自由大学の研究生から聞いた話では、海外の研究者ほど、日本のニッチな歴史のテーマを研究しがたるというのです。

日本国内が無理なら、海外の研究者でも、誰でも。
同じように「なぜ?」と興味を持つ人が調べてくれたらいいなと、密かに願いながら「こんなに色々気になることがこのエリアにあるんですよ」と欠片を拾い集めては発信を続けています。
この記事を読んでいる方におすすめの記事
右三つ巴紋と左三つ巴紋の違いとは?↓

右三つ巴紋と逆立狛犬と海のつながりとは↓